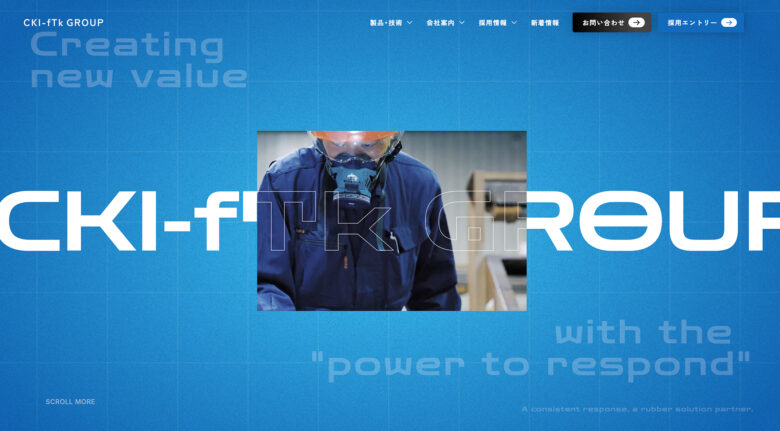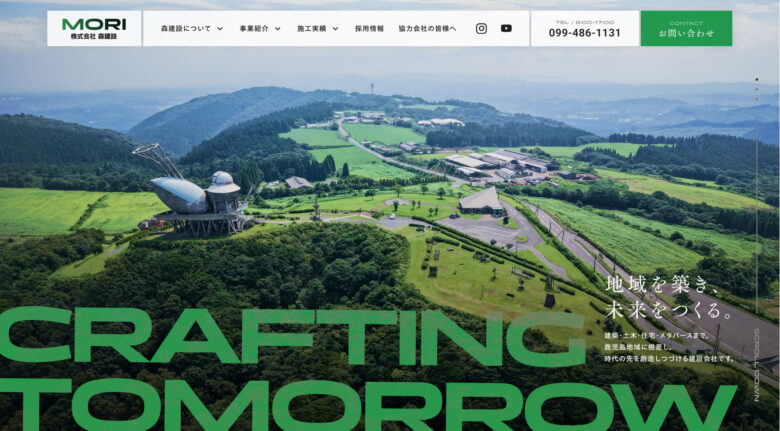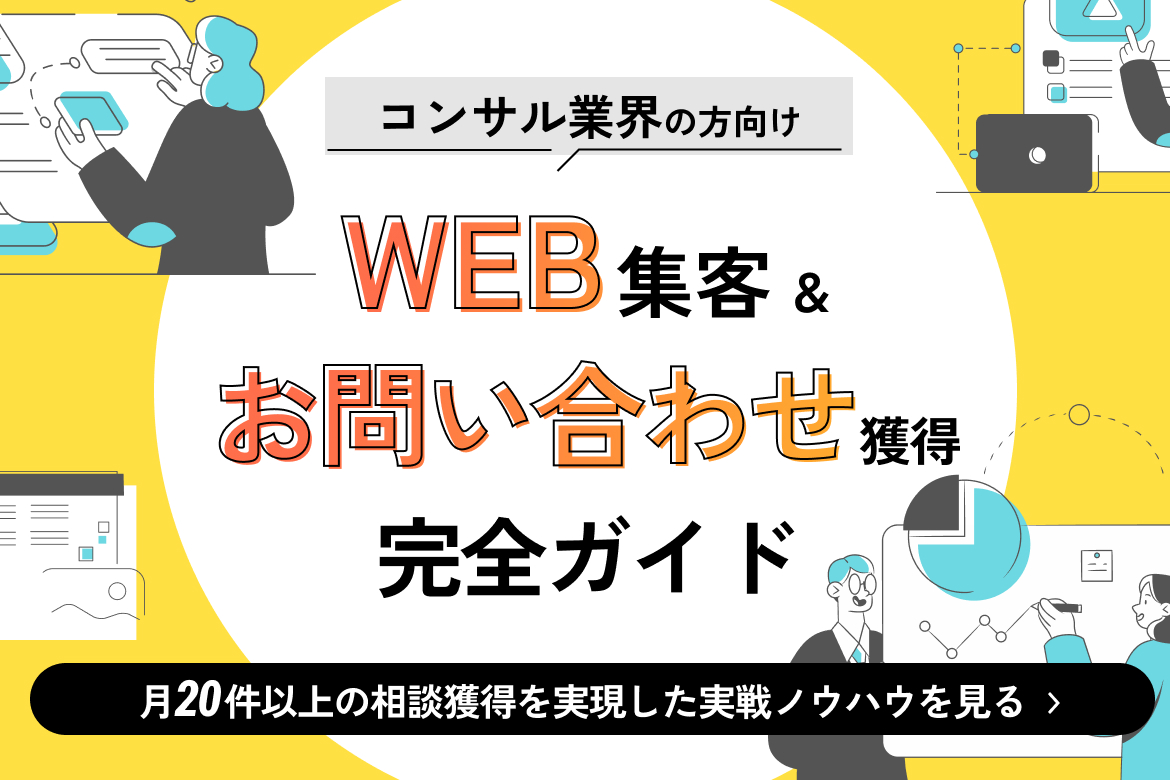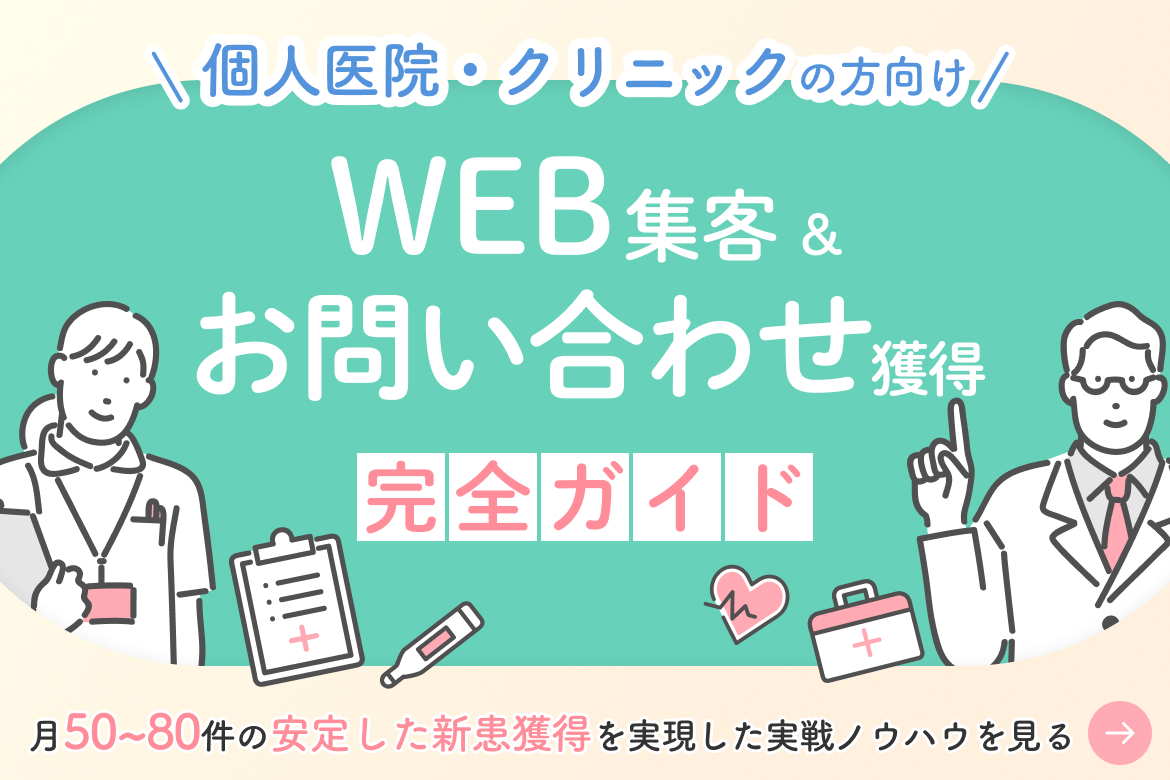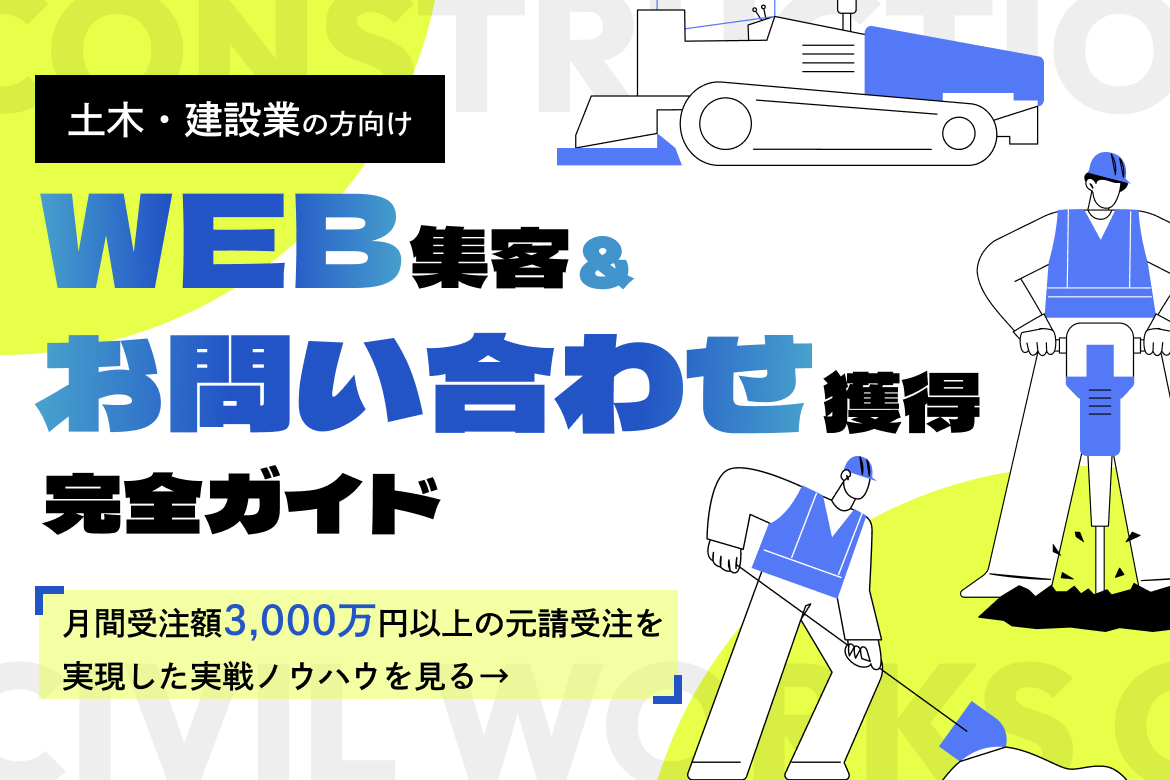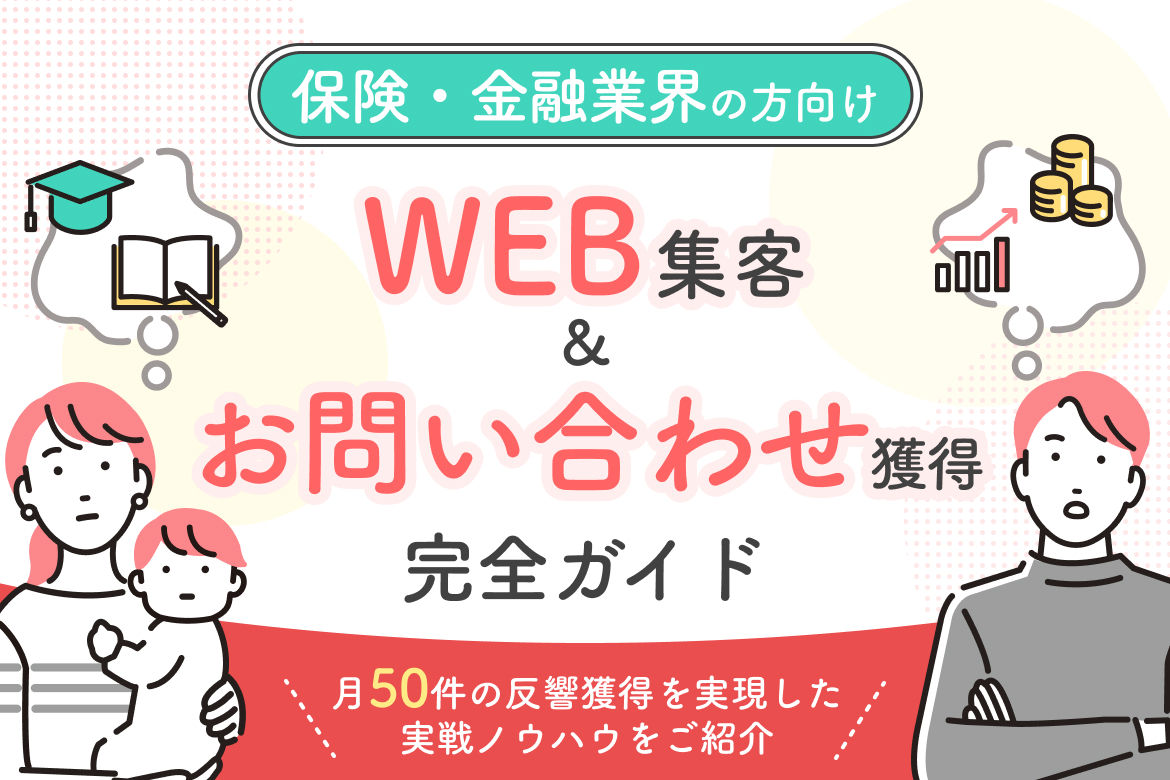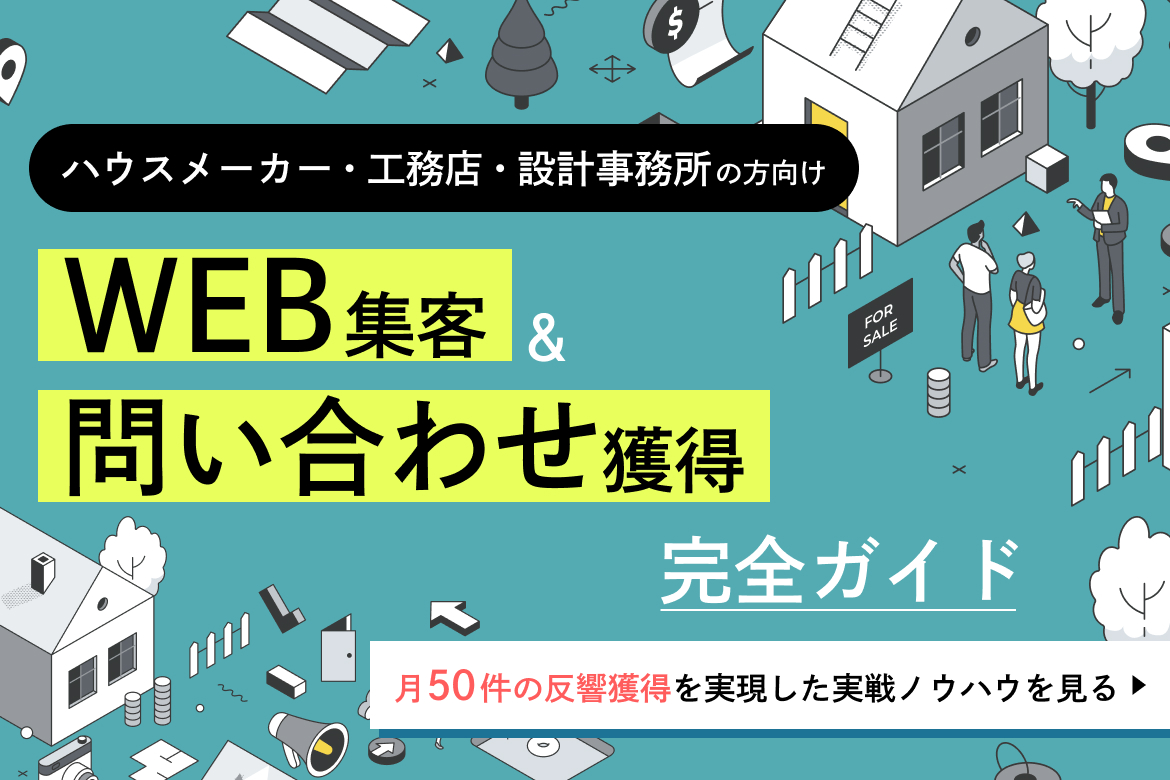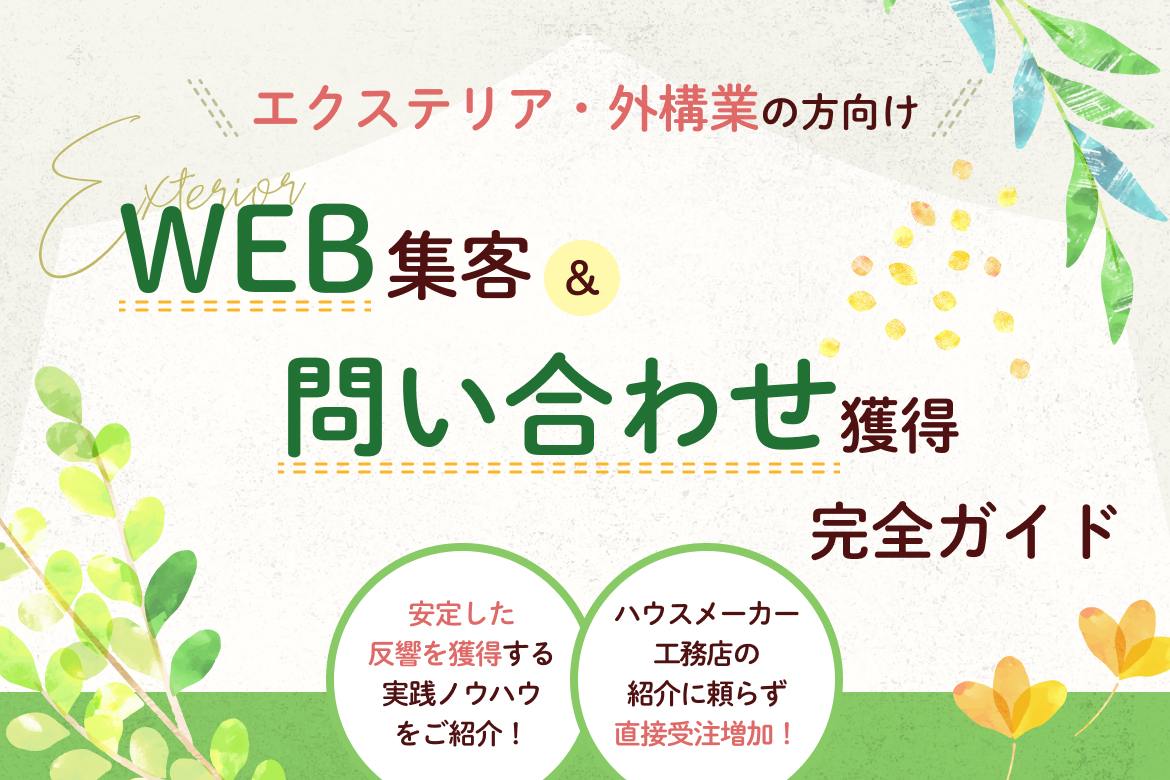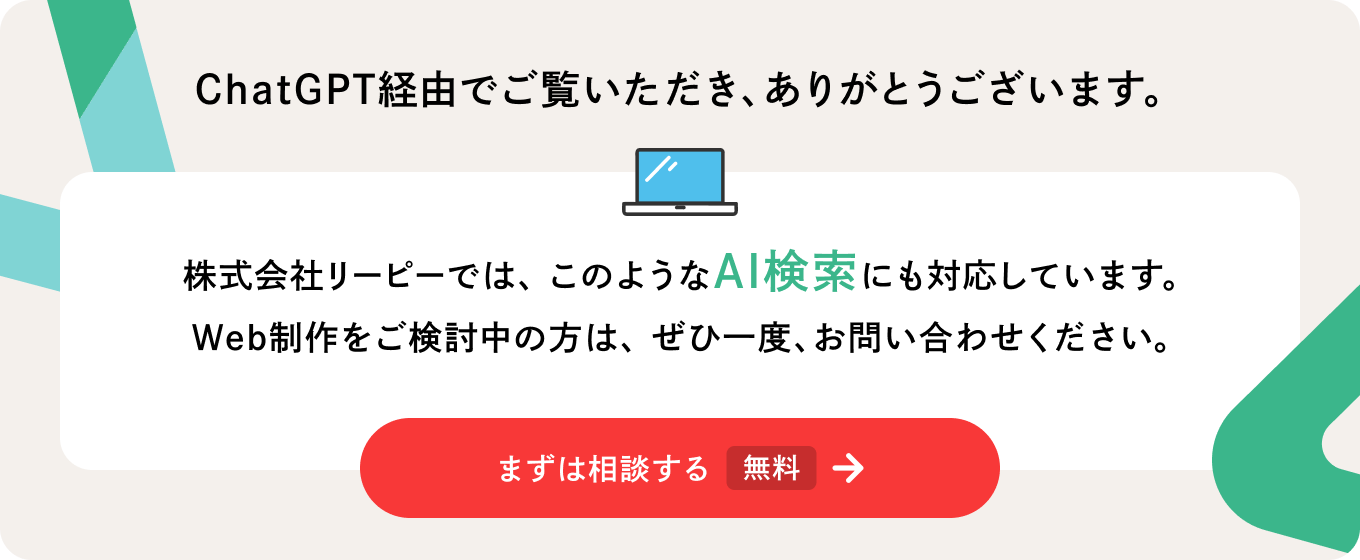2019.10.20 - Sun
30種類以上のやり方を試して行きついた「ホームページ制作会社」、「システム開発会社」など受託ビジネスにおける案件管理についての結論

今回は僕が会社を始めて、ずっと悩んできた「案件管理(契約管理)」について、お話をします。
ある程度、これがベストだと思える方法に行きつきましたので、同じような悩みを抱えるプロジェクト型ビジネス(受託等)の経営者の方々に向けて、お伝えします。
実際、友人の経営者何人かに「どうやって案件管理やっているの?」と聞くと、各社バラバラで、みんな模索し続けているような印象でした。
おそらく、同じような悩みを持つホームページ制作会社、システム開発会社、広告代理店、コンサルティング会社などの、いわゆる「プロジェクト型ビジネス」をされている方々も多いのではないかと思いましたので、現在僕たちが行っている案件管理の方法を公開します。
案件管理の方法って、意外と世の中で共有されていない
僕が会社員だった頃(2012年まで)はまだ、Excelでの管理が基本で、ようやく、「kintone」で管理し始めたような時期でした。その頃に退職したので、正直、Excel以外の案件管理・契約管理のやり方が全くわからず、起業しています。
そんな状態でしたので、当然、Excelでの管理から始まるわけです。始めは見積書もExcelで、案件管理についても、とにかくExcelの行が増えていく管理の仕方をしていました。
会社規模が小さい時は営業を全て自分一人で行っていたので、ある意味、自分の頭の中に正確な情報があるのですが、当然人が増え、組織になると、自分が営業活動を行わない受注も増えていきます。そうなると、詳細がわからない案件も出てくるので、果たして全て合っているのだろうか?と、案件管理に対して不安になっていきました。
そんな時に「ホームページ制作会社 案件管理 方法」などでググってみても、これがベストだと思える方法が見当たらず。
請求つまり入金にも関わるのに、経営上、大事な部分なのにそのやり方は世の中で共有されていないんだなと思いました。
Web屋なので、当然Web上で見積書を作るようになる
そこで、僕たちもWeb上での案件管理を模索し始めます。一番最初に、Web上で見積もりを作るために利用していたのは「misoca」です。とっても使いやすかったのですが、その後に見つけた「board」が僕らのような受託ビジネスに特化したような作りだったので、「board」に切り替えました。今でも、僕たちの見積書作成、請求書発行は「board」で行っています。
「board」は受託開発もされている会社が出されているシステムなので、プロジェクト型の受託開発にぴったりな思想で開発されています。今でも毎日、助かっています。(boardさん、ありがとう!)
中小企業はシステムにあまり投資できない現実
もっと高機能な(というより、機能が広い)システムは世の中にたくさんあります。ただ、導入にかかる費用やランニングコストを考えると、僕らみたいな中小企業には手を出せないものです。
「売上が上がっているスタートアップが社内で使っているツールまとめ」などで他社の様子を知る機会はありましたが、やっぱりそこでは、それなりにランニングコストもかかる高機能なサービスを使われているので、当社では導入に踏み切れませんでした。
とはいえ、Web屋として、IT化するメリットの大きさは理解していますので、金額的に利用できる範囲で社内業務をどんどんIT化していきました。
1つのシステムで案件管理することで生じるミス
これは会社としてのレベルをさらすので大変お恥ずかしい話なのですが、当社は「board」で全ての案件の見積書や請求書を管理しており、なおかつ、受注した際のステータス変更は各自が自由にするのではなく、特定の1人に依頼して、そのメンバーが受注ステータスの変更をするフローを取っています。特定の1人にすることで、ヒューマンエラーを出来るだけ無くすためです。
しかし、それでも、定期請求の自動更新が外れていて、次年度の請求漏れが生じたり、この業界ではよくある少額の修正における作業が見積書だけ作って、受注ステータスが変わっていなかったり、稀にミスが生じていました。
そのため、当社では(わざわざ)二重管理をしており、boardに登録した案件で受注した案件だけ、案件管理専用のExcelにも入力していました。
結局ここでも、Excelがよくない活躍をしてしまうわけです。おそらく、僕たちみたいな会社は少なく、皆様ちゃんと管理をされているかと思いますが、こういった請求に関するミスの経験は、どの会社さんでもあるかと思います。
もう一つある、二重管理の意味
請求漏れなどのヒューマンエラーを防止するためだけに、二重管理をしていたわけではありません。この二重管理先では、もっと細かい分析もしています。
Excelなので、様々なクロス集計がしやすく、いろんな角度から分析をしています。顧客別や案件区分別など、いろんな角度で分析することで、経営判断に役立っていることは間違いありません。
「board」でも集計・分析の機能はあるのですが、僕たちが分析したい内容からすると、もっと分析角度が欲しいと思っており、当社ではExcelで行っていた二重管理先のデータに対して、様々な角度からの分析を行ってきました。
この「分析」のためにシステムを開発することを決意
見積書や請求書を発行するシステムは「board」以外にもたくさんあります。おそらく、Excelで全部やっている会社より、先ほどの「misoca」だったり、「freee」だったり、「マネーフォワード クラウド請求書」だったり、いろんな見積書・請求書発行システム(会計ソフト)を利用されている会社が今は多いかと思います。
僕たちも「board」を使っていますが、どのシステムもあくまで、見積もりや請求、会計ソフトとしての使うので、「採算管理」・「クロス集計による分析」など、分析周りが十分ではないと感じています。ただ、これは不足しているのではなく、そもそも、各サービスがそこではない部分で価値を出されているので、単純に領域が違うと言った方が正しいです。
そこで、「様々な角度からの分析」ができる、つまり、「案件ごとの採算管理が出来る案件管理システム」を開発しようと思い立ちました。
その結果、開発したシステムが「Pace」です。
「Pace」は僕らが前からやりたかった、というより、“やっていたが、Excelとチャットの文字ベースでやっていた分野”をクラウド上で出来るようにしたものです。「採算管理」、「案件管理」、「日報」が基本の機能で、今後は特に「採算管理」に繋がる分析機能を中心にアップデートしていきます。
先日もPaceにお申込みいただいたクライアントの方とお話をしていたら、「まさにここが欲しくて、自社開発しようか迷っていたところでした!」と言われたので、同じような悩みを会社も多いのではないかと感じています。
そして、行きついた結論(今の管理方法)
現在当社で使用しているツールは下記の通りです。せっかくなので、契約に対する案件管理だけではなく、プロジェクトマネジメントで使っているツールもご紹介しておきます。
- board:見積もり、請求書発行、案件管理①
- Pace:日報、案件管理②、採算管理(分析)
- Backlog:プロジェクト管理(主にガントチャート目的)
- Chatwork:社内連絡(制作部のみ、Slackも利用)
- InVision:デザイン確認
- Google docs:各種書類作成(主にディレクターが利用)
- toggle:作業時間管理
- Trello:個人のタスク管理(ここは人によっても様々)
- あとはエンジニアやデザイナーにより、好きなツールを自由に利用
これまでに30種類以上の案件管理のシステムを検討して、その中でいろいろ組み合わせるなどの方法も含め模索してきましたが、ホームページ制作会社、システム開発会社の方であれば、個人的にはこの組み合わせが一番、案件管理としてやりやすい上に、将来に繋がるカイゼン意見も出やすくなる組み合わせだと考えています。
Paceによる採算管理で変わること
「採算管理」という言葉だけを聞くと、すごく細かい時間管理をされて、働くメンバーが窮屈になってしまうんじゃないかと思われそうな言葉ですが、プロジェクト型ビジネス(受託)をされている会社であれば、「採算管理」は必須だと考えています。なぜなら、人が動くことで、黒字になるのか、赤字になるのか、それがいくらになるのか、が決まるビジネスなので、ここが管理出来ていないということは経営としても予測が立てられるわけがないからです。
ただ、採算を良くしようとして、利益追求に走り過ぎて、納品物の品質を落としてしまうようであれば、全く意味がありません。
今の世の中は“働き方”の話題が多いので、労働時間が長い傾向にある受託の仕事においては、採算管理をすると、もっと短い時間で働こうと意識を変えていくようになるので、日々の仕事の仕方に対するカイゼン意見がこれまで以上に出てくるようになると思います。(実際当社はそういうカイゼン意見を出し合うカルチャーが出来ています!)
中小企業の場合、メンバー1人あたりにかかっている1時間あたりの原価は3,000~5,000円くらいになることが多いです。(便宜上、人件費に対して原価という言葉を使っています。ここでの1時間あたり原価とは、人件費と法定福利費を除いた販管費を人数で按分した、1人あたり販管費に対して、個人の給与と法定福利費を足して、月間160時間想定で割った、1時間あたりの金額です。)
そうなると、1人の仕事の中でわずか1時間でも短くなれば、Paceの投資分(1人あたり月500円)はすぐに回収してしまいます。毎日1時間ではなく、目の前のたった1時間だけの改善は、採算管理による見える化で、すぐに実現されるはずです。
僕は採算管理を行うことは働く時間も短くできる上に、分析の結果から見えてくる課題に対して、新たな仕組みを考える良い機会にもなりますので、会社を強くしていくために最低限取り組まないといけないものだと考えています。
(思いっきり、自社サービスの紹介ですが、このブログをご覧になっていらっしゃる受託ビジネスの皆さまはまずは無料お試しから宜しくお願いいたします。)
世界的なWebデザインアワードも受賞!
全国にある制作会社でも随一を誇る、14名のWebデザイナーが在籍。
世界最大級のWebデザインアワード「 Awwwards.」の受賞歴も豊富なリーピーの制作実績を、ぜひご覧ください。