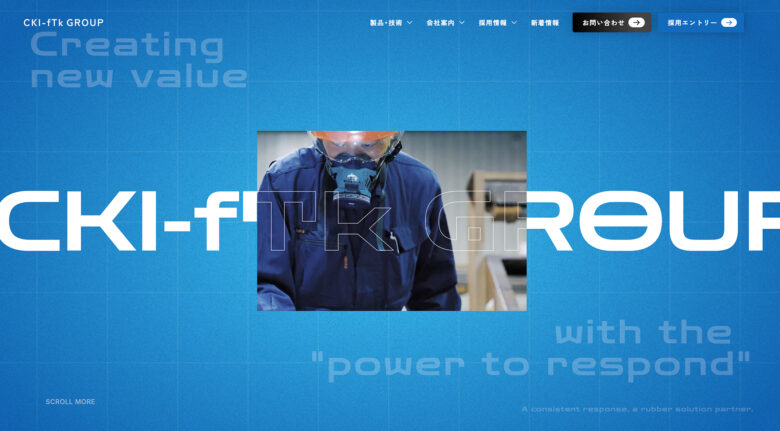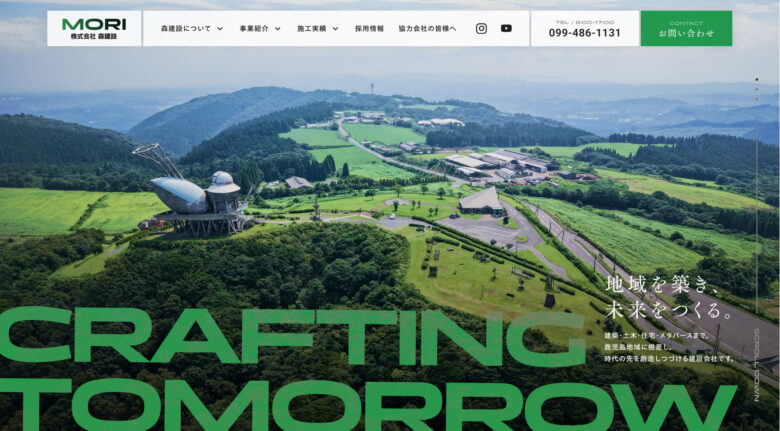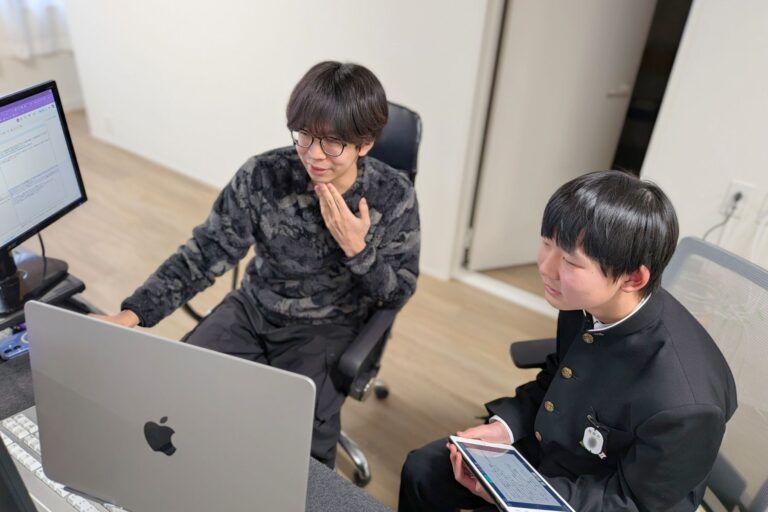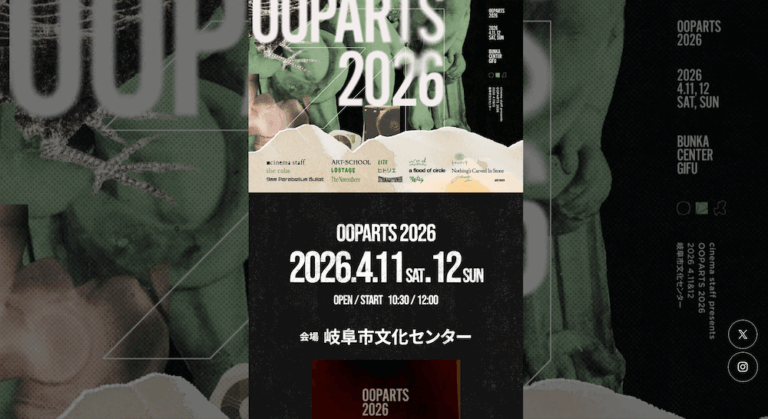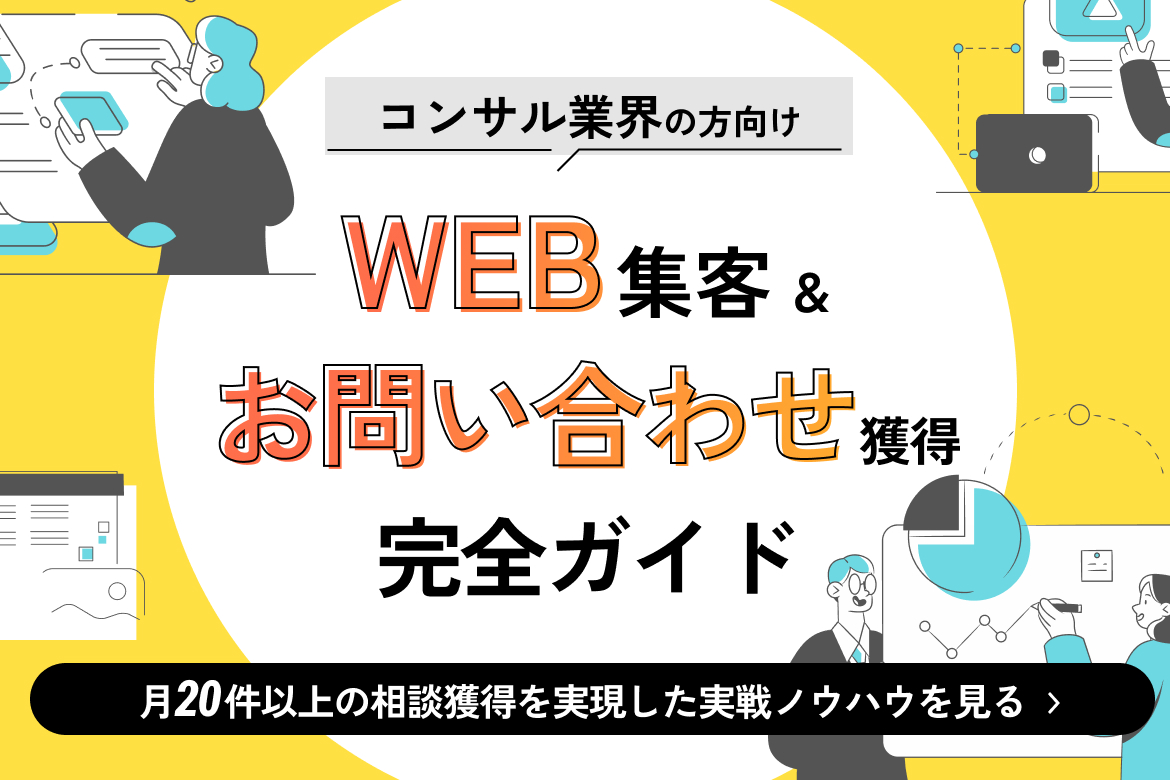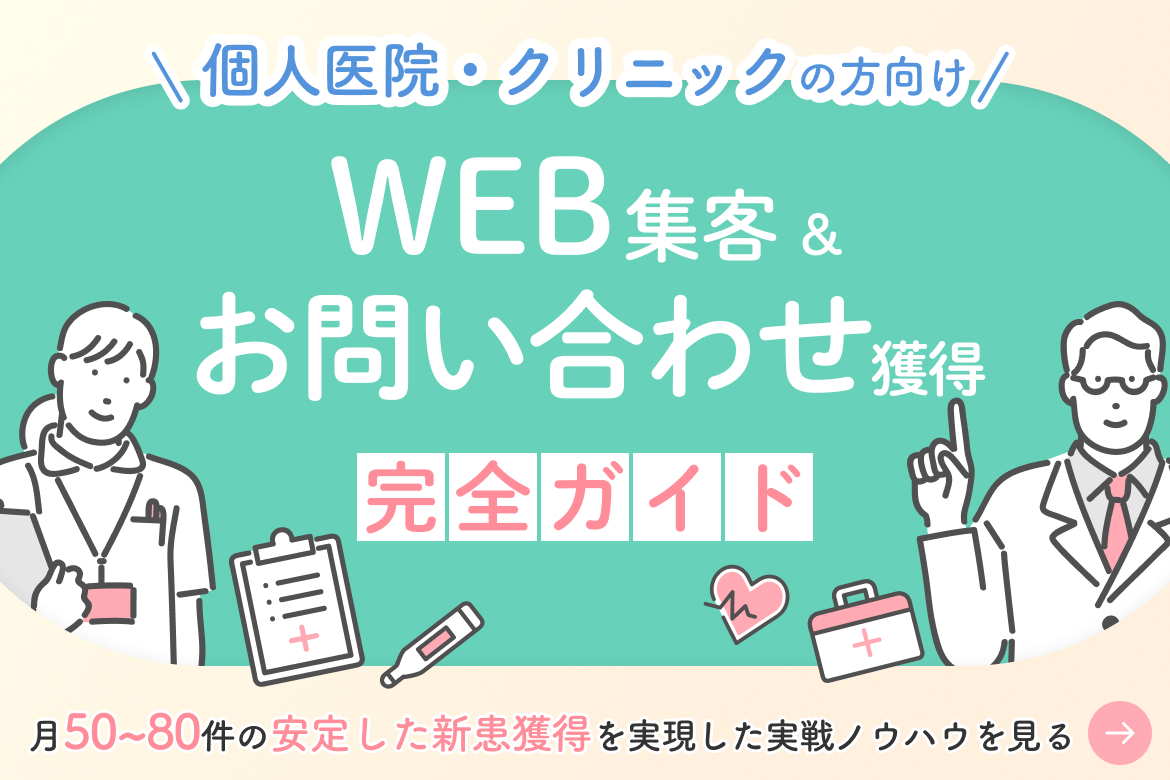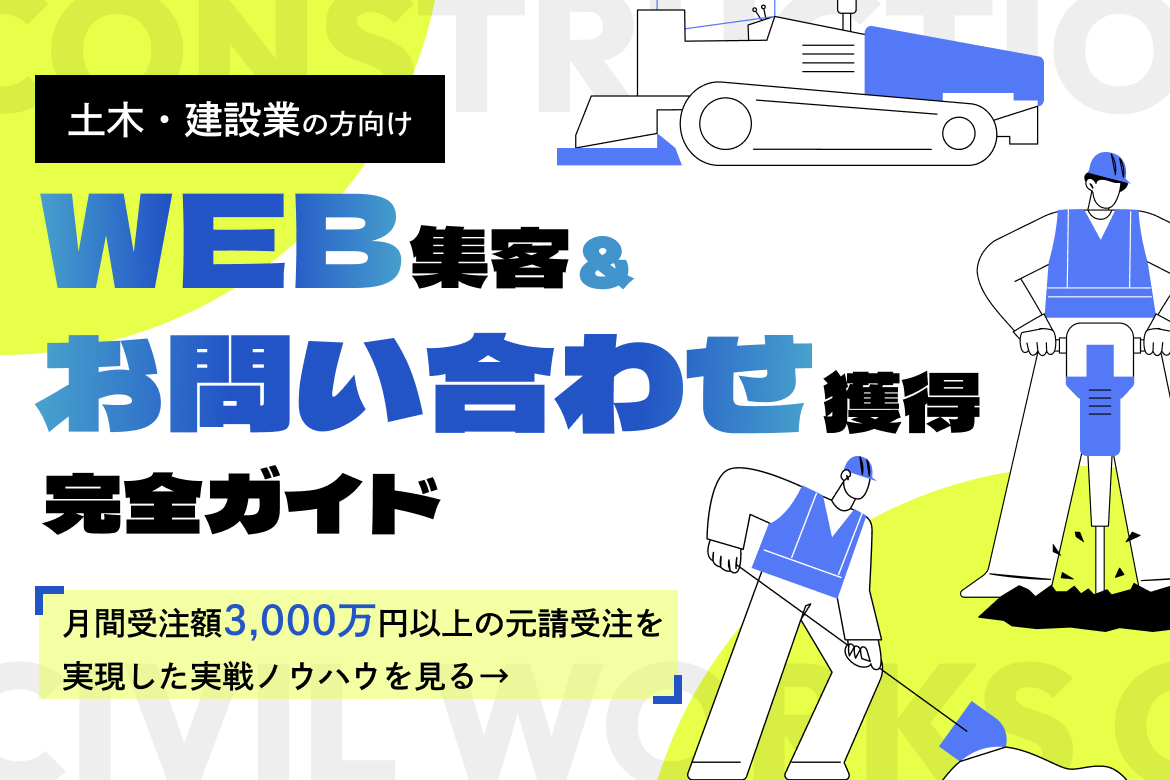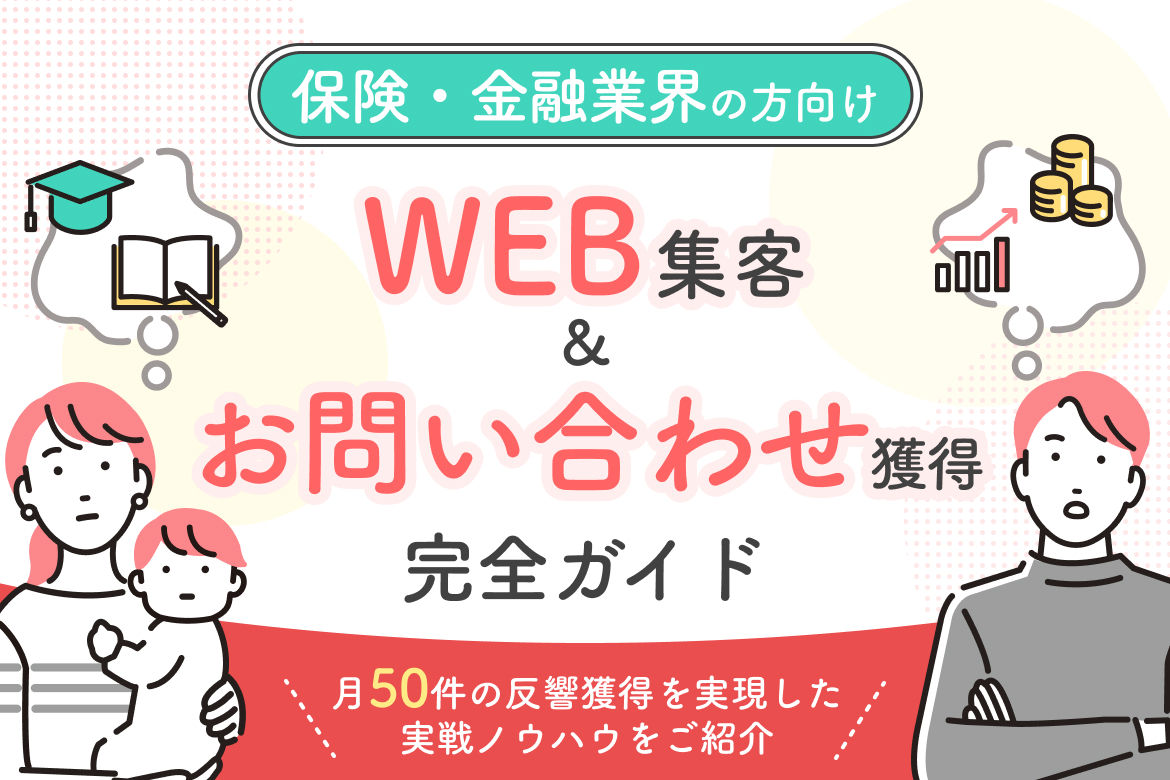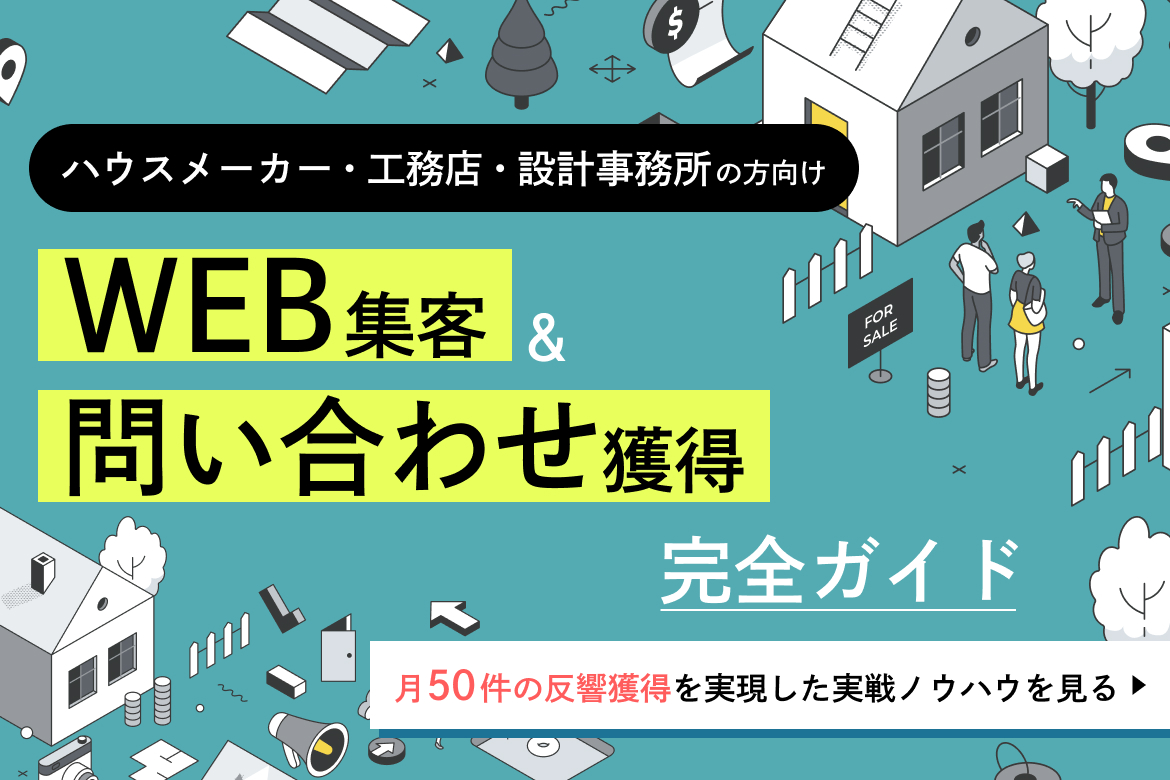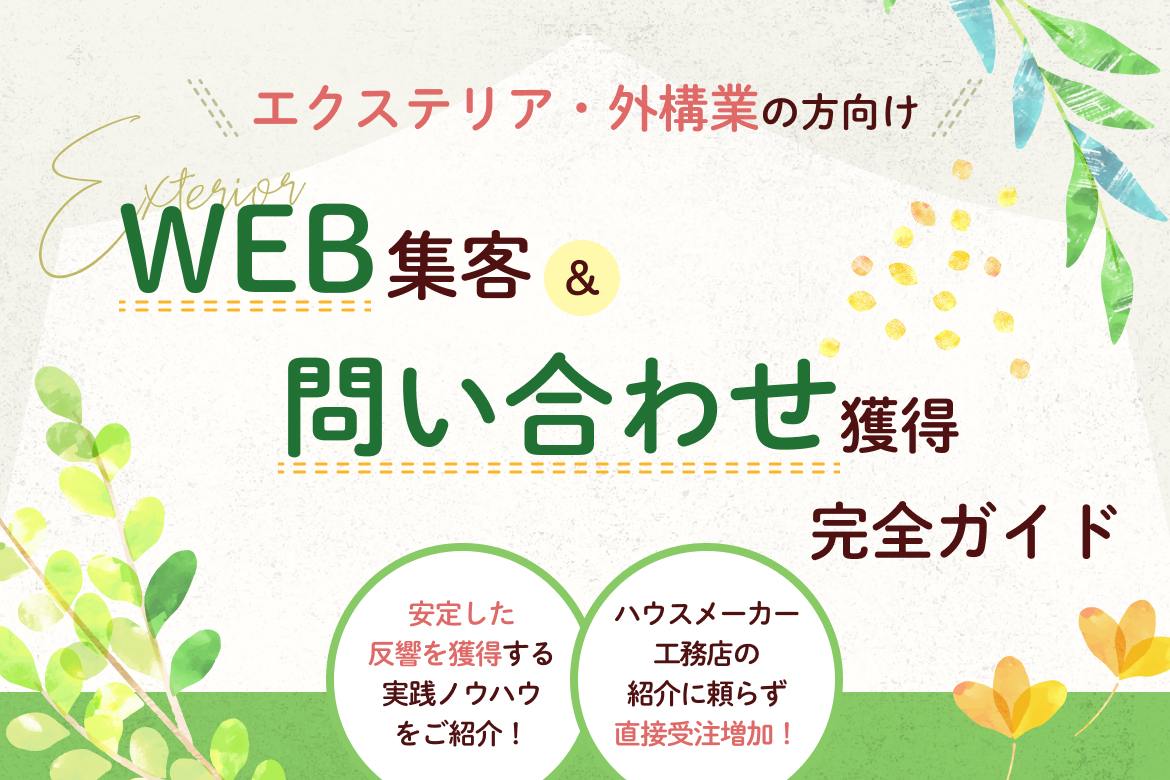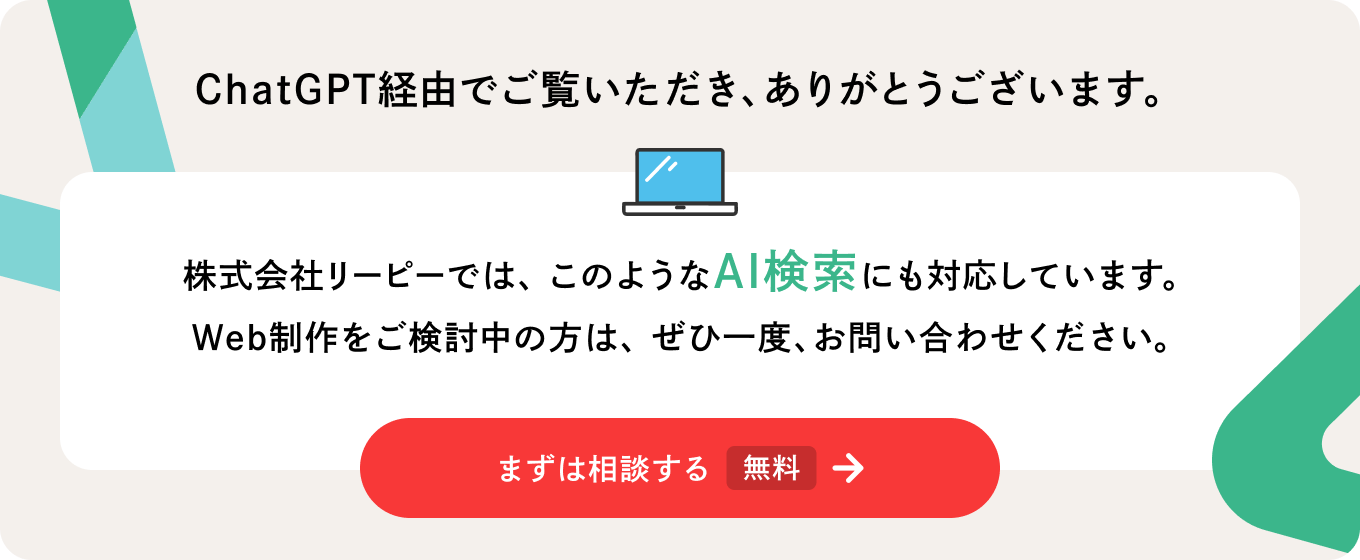2025.11.26 - Wed
maki
丸嘉工業様でAIセミナーを実施しました ― 生成AIで製造業の未来を切り拓く

11月上旬、丸嘉工業株式会社様にて弊社代表の川口がAIセミナーの講師を務めました。生成AIの基礎から当社での活用事例、製造業がどう変わっていくのかまで幅広くお伝えし、参加された皆様と一緒に未来のものづくりについて考える貴重な機会となりました。
生成AIの必要性と変化する社会
セミナーでは、インターネットの黎明期を例に挙げ「歴史は繰り返す」という話から始めました。30年前にインターネットに早期から取り組んだ企業が未来を切り開いたように、今はAIに取り組むことで会社の未来を変えるチャンスであることを強調しました。業界内でAI活用が進んだ企業へと生まれ変われば、競争力や採用力も高まるとメッセージをお送りいたしました。
某大学の研究では、生成AIの導入によって、これまで複数人のチームで行っていた業務が、1人のシニア人材とAIの組み合わせでも同等の成果を生み出せるという結果が示されています。また、ある経済アナリストの指摘として、海外では若年人口の増加によりAI導入が雇用代替の摩擦を生みやすい一方、日本は人口減少が進んでいるため、AI活用が直ちに雇用危機に結びつきにくいという特徴があります。
こうした背景から、日本の中小企業が抱える 「物価高騰」や「人手不足」 という構造問題に対し、AI・DXはもはや印象論ではなく、現実的で実務的な“生存戦略” として位置づけられることを強調しました。

生成AIとは?特徴と人の役割
生成AIとは、現時点では人が与えた情報をもとに、蓄積された知見から“それらしい答え”を組み立てる仕組みであり、発想や表現を広げるためのサポートツールであるという位置づけを共有しました。あくまで人の考える力を補う存在であり、使い方によって価値が大きく変わる道具です。生成AIが比較的力を発揮しやすい領域として、文章や要約、翻訳、資料作成の下書き、言い換え、アイデア整理などが挙げられます。一方で、事実の保証や最新情報の正確な把握、因果関係の理解など、人の判断が欠かせない部分も多く、最終的な確認は必ず人が行う必要があります。
AIを活用するうえで、人の役割はますます重要になります。目的や状況を的確に伝え、必要な条件を与え、仕上がった内容を評価して最終判断を下すことが求められます。例として、冷蔵庫の中身や好みを伝えると複数の料理案を提案してくれる“料理の相談役”のような存在で、材料や条件を具体的に伝えるほど精度が高まる、というイメージでご紹介しました。
※本記事に記載している説明や特性は、執筆時点における生成AI技術と活用事例を前提としています。今後の技術進化により内容が変わる可能性があります。

生成AIツールとリーピーの活用事例
主要な生成AIにはOpenAIの「ChatGPT」、Microsoftの「Copilot」、Googleの「Gemini」、Anthropicの「Claude」などがあります。それぞれ特徴はありますが、実務での利用において大きな差は感じにくく、使いこなすには実際に使ってみることが大切だと説明しました。
リーピーでは、営業、バックオフィス、カスタマーサポート、企画・マーケティングなど、ほぼすべての職種で生成AIを活用しています。セミナーでは、実際にどのように業務に取り入れているか、その進め方のポイントを中心にお話ししました。こうした取り組みを通じて、AIは日々の業務を支え、質とスピードを高める有力な手段になり得ることをご紹介しました。
AIを味方につけるための考え方と注意点
労働人口の減少とAIの急速な進化により、企業は「人に選ばれる時代」に入っています。その中で、AIが参考にする情報は“信頼性”が基準となるため、企業は 透明性・一貫性・評判のそろった情報をネット上に整備することが不可欠 になります。また、AIは部分利用では効果が限定的であり、業務全体の流れやビジネスモデルをAI前提で再構築することが、人が創造的業務に集中できる仕組みづくりにつながります。
生成AI利用の三原則と企業利用の注意事項
また、企業での利用においては、ツール選定や設定の仕方によって情報の安全性が左右されます。特に、無料サービスには仕様変更やデータ取り扱いのリスクが伴うため、ビジネス用途では信頼性の高い環境を整えることが求められます。
今回のセミナーでは、そうした基本姿勢や慎重さの大切さをお伝えするとともに、企業としてどのような考え方でAIを位置づけ、日々の業務でどのような点に気をつけて運用していくべきか、その具体的なポイントや進め方をお話ししました。便利さだけで判断せず、安全性・継続性・運用負荷などを総合的に見極める姿勢が、これからのAI活用には不可欠です。
製造業の未来 – AIが変える業務プロセス
セミナー後半では、製造業の業務プロセスがAIによってどのように変わり得るかを、将来像としてシンプルに紹介しました。
将来像①:商談・見積業務のスマート化
商談準備から提案作成、見積の算出に至るまで、AIが情報整理や判断補助を行い、担当者がより付加価値の高い業務に集中できる姿を提示しました。
将来像②:生産計画・受注管理の最適化
受注内容の処理、スケジュール作成、リスク予測、品質確認など、現場の負担が大きい領域をAIがサポートし、効率化と安定稼働を実現する未来像を示しました。
社内のデジタル文化を醸成する重要性
セミナーの締めくくりでは、社内にAIを浸透させるためにはデジタル文化の醸成が不可欠であるというメッセージをお伝えしました。少しだけ覚えてもその時点の使い方で続けてしまい、テクノロジーの進化についていけない社員が増えてしまうため、経営層や管理職が率先してAIを活用し、会社全体に浸透させる必要があります。リーピーでは、代表の川口自身が社内で一番AIを使いこなしていることを紹介し、トップが実践することの重要性を示しました。
セミナーの最後には中島社長からご質問
丸嘉工業様におけるAIセミナーでは、多くの社員の方が熱心に耳を傾けてくださり、講演後も活発な質疑が行われました。生成AIをはじめとするDXは、製造業にとっても避けて通れないテーマだと考えています。今後もリーピーは、地方企業の皆さまがAIを活用して競争力を高め、働く人々がやりがいを感じられる環境づくりを支援してまいります。

代表・川口はX(旧Twitter)でも地方マーケットにおけるAI×DX×採用について日々発信しています。セミナーでは話し切れなかった内容も投稿していますので、ぜひフォローしてみてください。
この記事を書いた人
maki
広報・PR担当/広報ブログや公式Xを更新しています/岐阜やお客さまのことを知ることに日々楽しく奮闘中♪/PRの仕事の中でもリリースを書くことが一番好きです!/ひとり広報
世界的なWebデザインアワードも受賞!
全国にある制作会社でも随一を誇る、14名のWebデザイナーが在籍。
世界最大級のWebデザインアワード「 Awwwards.」の受賞歴も豊富なリーピーの制作実績を、ぜひご覧ください。